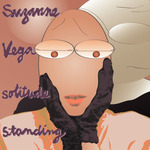2010年12月19日
『IZUMIYA・SELF COVERS』 by 泉谷しげる
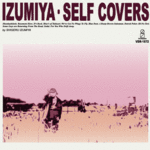
まごう事なきロック・アルバムである。頑強で強固で盤石の音楽を聴く事が出来る。と、同時に、頑迷で頑固で融通の利かない心情が吐露されている。
read details 『IZUMIYA・SELF COVERS』 by 泉谷しげる
posted =oyo= : 14:27 | comment (0) | trackBack (0)
2010年11月22日
『エレクトリック・レディランド (ELECTRIC LADYLAND)』 by ジミ・ヘンドリックス (The Jimi Hendrix Experience) disc two
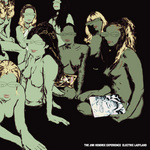
前回のdisc oneでは、作品のフォーマットの話に終始したから、今回はジミ・ヘンドリックス (Jimi Hendrix) の音楽について語りたい。
なにやら群盲象を撫でる (den Wald vor lauter Baeumen nicht sehen) 様な気がしないでもないのだけれども、音楽を語る事ソレ自体が、そういう徒労じみた行為なのだから。
と、自戒の様な諦念の様な戯言をほざいてから、書き始めてみる。
posted =oyo= : 18:51 | comment (4) | trackBack (0)
2010年11月21日
『エレクトリック・レディランド (ELECTRIC LADYLAND)』 by ジミ・ヘンドリックス (The Jimi Hendrix Experience) disc one
posted =oyo= : 22:36 | comment (0) | trackBack (0)
2010年10月17日
『ジミー・ジュフリー 3, 1961 (Jimmy Giuffre 3, 1961)』 by ジミー・ジュフリー 3 (Jimmy Giuffre 3)
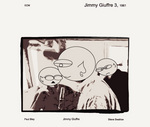
不思議なアルバムである。
癒し系のヒーリング・ミュージック (Healing Music) として聴く事も出来るし、とってもアグレッシヴなフリー・フォームのジャズ (Free Jazz) として聴く事も出来る。
それは、クラリネット (Clarinet)、ピアノ (Piano)、ベース (Bass) という変則的な構成に所以するものかもしれないし、この作品に関わったミュージシャンの出自とこれ以降の活動に起因するものかもしれない。
それとも、この作品を発表 / 発売したレーベルの所作によるものなのだろうか?
read details 『ジミー・ジュフリー 3, 1961 (Jimmy Giuffre 3, 1961)』 by ジミー・ジュフリー 3 (Jimmy Giuffre 3)
posted =oyo= : 20:20 | comment (0) | trackBack (0)
2010年09月19日
『軋轢』 by FRICTION

例えば、"日本のロック"名盤 (Japanese Rock Best Album) **選を編めば、確実にエントリーする作品であるのは間違いないだろうし、世界中の作品をその対象とした"パンク"名盤 (Punk RocK Greatest Album) **選を編めば、それにも確実にエントリーされなければならない作品である。
にも関わらずに、この作品は、到達点でもなければ出発点でもない。この作品に関わったモノ達にとっては、単なる通過点のひとつでしかないのだ。
posted =oyo= : 12:24 | comment (0) | trackBack (0)
2010年08月15日
"HERE COME THE WARM JETS" by ENO

あらためて書くまでもないことだけれども、今年の夏は猛暑日 (Heat Wave) が続いていて、しかも今日は終戦記念日 (Victory Over Japan Day)。65年前の今日も相当暑かったと聴いている。
映画『日本のいちばん長い日 (Japan's Longest Day)』[岡本喜八 (Kihachi Okamoto) 監督作品] で、いちばん印象的なシーンも、黒沢年雄演じる陸軍省軍事課 (The Military Affairs Section Of The Army Ministry Of Japan) 畑中健二 (Kenji Hatanaka) 少佐 (Major) が、油の切れた自転車を必死にこいで東京を奔走する、その汗まみれの姿なのだ。
だから嗚呼、今日の東京の風は、ウォーム・ジェット (Warm Jets)どころの騒ぎぢゃあない、これはホット・ジェット (Hot Jets)、もしくはヒート・ジェット (Heat Jets)と呼ぶべきものだ、とくだを巻 (Ramble On) きたくなるが、気にしないでくれ。
これは本題なんかぢゃあない。単なる導入部なんだ。
read details "HERE COME THE WARM JETS" by ENO
posted =oyo= : 19:43 | comment (0) | trackBack (0)
2010年07月19日
『地獄に堕ちた野郎ども (DAMNED DAMNED DAMNED)』 by ダムド (THE DAMNED)
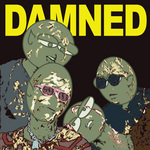
シングル・レコードを最も早く発表し、デヴュー・アルバムを最も早く発表し、そして最も早く解散したその上に、最も早く再結成したパンク・バンド。
ダムド (THE DAMNED) をパンク・バンドという切り口で紹介するには、最も早くて最も解りやすい口上が、上の一文である。あと、もうひとつやふたつやみっつくらいは"最も早い〜パンク・バンド"という称号があてはまる様な気がしたけれども、忘れてしまった。
でも、まぁ、いいや。
1977年発表の彼らのファースト・アルバムである本作『地獄に堕ちた野郎ども (DAMNED DAMNED DAMNED)』を紹介するには、これで充分だろう。
read details 『地獄に堕ちた野郎ども (DAMNED DAMNED DAMNED)』 by ダムド (THE DAMNED)
posted =oyo= : 00:17 | comment (0) | trackBack (0)
2010年06月20日
"BASS ON TOP" by PAUL CHAMBERS
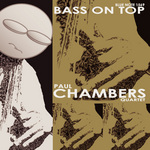
マイルス・デイヴィス (Miles Davis)・クインテットと呼ばれるユニットはふたつあって、ジョン・コルトレーン (John Coltrane : ts)、レッド・ガーランド (Red Garland : p)、ポール・チェンバース (Paul Chambers : b)、フィリー・ジョー・ジョーンズ (Philly Joe Jones : dr) による第一期 [1955年〜1960年] と、ウェイン・ショーター (Wayne Shorter : ts)、ハービー・ハンコック (Herbie Hancock : p)、ロン・カーター (Ron Carter : b)、トニー・ウィリアムス (Tony Williams : dr) による第二期
[1964年〜1968年] である。
余談だけれども、後にV.S.O.P. : Very Special Onetime Performanceとして再結集する後者のサウンドの要はウェイン・ショーター (Wayne Shorter : ts) でもハービー・ハンコック (Herbie Hancock : p) でもなくてトニー・ウィリアムス (Tony Williams : dr) だと思っている。
その理由は今回は書かないけれども、それと同じ様な理由で、前者の要はポール・チェンバース (Paul Chambers : b) だと思っているのだ、実は。
ちなみに第二期のベーシストであるロン・カーター (Ron Carter : b) に関しては、こちらで述べられている論調を肯定したくなるのだが、果たして...。
read details "BASS ON TOP" by PAUL CHAMBERS
posted =oyo= : 20:30 | comment (0) | trackBack (0)
2010年05月16日
『追憶のランデヴー (Versions Jane)』 by ジェーン・バーキン (Jane Birkin)
この台詞。言った方のおとこからみれば、おもいっきりの褒め言葉のつもりかもしれないが、果たして、言われた方のおんなには、どんな言葉として響くのか。
だからと言って、周りの女性達に感想を求めるのも野暮というものだし、それ以前に、この言葉が当て嵌まる様な御婦人には、残念ながらぼくの周囲にはいない。
にも関わらずに、こんな言葉をふと想い出してしまったのは、本稿の主人公、ジェーン・バーキン (Jane Birkin) が、正にこの言葉どおりの女性だからだ。
read details 『追憶のランデヴー (Versions Jane)』 by ジェーン・バーキン (Jane Birkin)
posted =oyo= : 20:23 | comment (0) | trackBack (0)
2010年04月18日
"Distinto, diferente" by JUAN DE MARCOS AFRO CUBAN ALL STARS
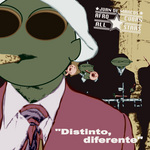
もうもうと感じる熱波と、倦怠感を促す湿度を感じさせるジャケットに魅入られて、ただそれだけで購入してしまったのがブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ・バンド (Buena Vista Social Club Band) のファースト・アルバム『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ (Buena Vista Social Club)』。
その際は、そのCDの中でどんな音楽が奏でられているのかも解らず、ライ・クーダー (Ry Cooder) によるプロジェクトである事も解らずに、購入してしまった。
1997年の事である。
そして、そこから促されるかの様に、本稿の主役であるアフロ・キューバン・オール・スターズ (Afro Cuban All Stars) にも出逢ったのだが、さて。
read details "Distinto, diferente" by JUAN DE MARCOS AFRO CUBAN ALL STARS
posted =oyo= : 19:48 | comment (0) | trackBack (0)
2010年03月21日
"HOT RATS" by FRANK ZAPPA
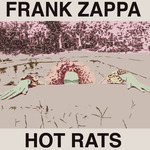
フランク・ザッパ (Frank Zappa) のアルバム・ジャケットは大別すると、カル・シュンケル (Cal Schenkel) による悪趣味極まりないヴィジュアルか、それとも、フランク・ザッパ (Frank Zappa) ご本尊の大アップのどちらか、もしくはその両方だったりするのだけれども、本作品は幾分、ニュアンスが違う。
廃墟を想わせる石造りのオブジェ [もしかすると地下納骨堂 (Columbarium) の入口かもしれない] に潜むカーリー・ヘア (Curly Hair) の女性がその頭部と両掌だけをのぞかせている。
そのミステリアスな雰囲気と変調させられた色彩は、なんとなくブラック・サバス (Black Sabbath) のファースト・アルバム『黒い安息日 (Black Sabbath)』や映画『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド (Night Of The Living Dead)
』 [ジョージ・A・ロメロ (George A. Romero) 監督作品] のヒロイン(?) カレン (Karen Cooper) [演:カイラ・ション (Kyra Schon)] を連想させたりもする。
しかし、一見、シンメトリー (Symmetry) に観えるそのヴィジュアルは、微妙に傾いでいて、微妙に歪んでいる。
そして、勿論、これまで観て観ないふりをしてきたけれども、そのヴィジュアルを挟む格好で、『FRANK ZAPPA』『HOT RATS』と大書きされているのだった。
しかも、だめ押しで指摘すると、このアート・ワークもカル・シュンケル (Cal Schenkel) の手によるのである。
read details ""HOT RATS" by FRANK ZAPPA"
posted =oyo= : 21:51 | comment (0) | trackBack (0)
2010年02月21日
"THE COMPLETE LESTER YOUNG" by LESTER YOUNG
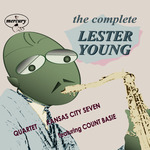
レスター・ヤング (Lester Young) は、ぼくにとっては謎だらけの人物である。
そもそも彼を知るきっかけとなったのが、ジェフ・ベック (Jeff Beck) とジョニ・ミッチェル (Joni Mitchell) とモノクローム・セット (The Monochrome Set) なのだから、そのみっつの焦点を紡いでみたとしても、茫洋とした人物像が、姿を現す訳ではない。
read details "THE COMPLETE LESTER YOUNG" by LESTER YOUNG
posted =oyo= : 21:25 | comment (0) | trackBack (0)
2010年01月24日
"BLACK SEA" by XTC

XTC(エックス・ティー・シー)を聴くことは、迷路 (Maze) の中を歩むのに似ている。
なにもそれは、彼らの『ワンダーランド (Wonderland)』のPVの中で、少女が迷路 (Maze) にも似た庭園を奔り惑っているからではない。それに第一、この曲は『ママー (Mummer)』 [1983年発表作品] に収録されている。本作品ではないのだ。
read details "BLACK SEA" by XTC
posted =oyo= : 21:07 | comment (0) | trackBack (0)
2009年12月27日
『フー・アー・ユウ (WHO ARE YOU)』 by ザ・フー (THE WHO) SIDE TWO
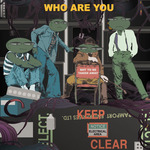
『フー・アー・ユウ (WHO ARE YOU)』 by ザ・フー (THE WHO) SIDE ONEでは、この作品のタイトルにふたつの解釈があると書いた。
ひとつは『フー・アー・ユー (Who Are You) / お前は誰だ』。
そしてもうひとつは『オレを連れ去ろうとする、お前は誰だ (NOT BE TAKEN AWAY - WHO ARE YOU)』、これはキース・ムーン (Keith Moon) の死をうけて、偶発的にというか、こじつけがましく読んだものだけれども。
ここでは、もうひとつの解釈の可能性を追っかけてみる。
read details 『フー・アー・ユウ (WHO ARE YOU)』 by ザ・フー (THE WHO) SIDE TWO
posted =oyo= : 00:20 | comment (0) | trackBack (0)
2009年12月20日
『フー・アー・ユウ (WHO ARE YOU)』 by ザ・フー (THE WHO) SIDE ONE
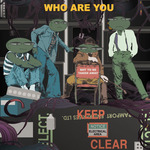
古ぼけた作業用の椅子に、『持ち出し禁止 (NOT TO BE TAKEN AWAY)』と書かれた文字が『オレはまだここにいたいんだ (NOT BE TAKEN AWAY)』と読めてしまう。
キース・ムーン (Keith Moon) の遺作である。
read details『フー・アー・ユウ (WHO ARE YOU)』 by ザ・フー (THE WHO) SIDE ONE
posted =oyo= : 21:06 | comment (0) | trackBack (0)
2009年11月22日
"Solitude Standing" by Suzanne Vega
最初は『トムズ・ダイナー [TOM'S DINER]』だった。
ア・カペラ (a cappella)、というよりも呟く様に唄われるその声が、情緒的なものや叙情的なものを排している。唄われている街の叙景がそのまま、今ここにある様に聴こえてくるのだ。
read details "Solitude Standing" by Suzanne Vega
posted =oyo= : 14:34 | comment (0) | trackBack (0)
2009年10月18日
『ユーズド (UZED)』 by ユニヴェル・ゼロ (UNIVERS ZERO)

印象的なピアノ (Piano) の残響音に導かれてオープニング・ナンバー『予感 (Presage)』が始る。この響きに引き込まれさえすれば、後は彼らの演奏に惑溺出来るのだ。
read details 『ユーズド (UZED)』 by ユニヴェル・ゼロ (UNIVERS ZERO)
posted =oyo= : 16:02 | comment (0) | trackBack (0)
2009年09月20日
『20 ジャズ・ファンク・グレイツ』 by スロッビング・グリッスル("THROBBING GRISTLE bring you 20 Jazz Funk Greats" by Throbbing Gristle)
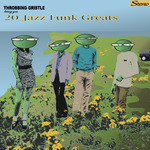
可能性の音楽。この作品を聴く度に、音楽に不可能はないし、音楽というメディアで表現できないものはなにもない、そう想えてならない。
にも、関わらずに、その音楽そのものを語る術があまりに乏しく、不自由極りない、そんな徒労にも似た絶望感に打ちのめされるのも、この作品だ。
1979年発表作品、そして国内盤として僕が手に入れるのがその三年後の1981年。
このタイムラグだけが、その遠因であるとは決して言えないと、想う。
posted =oyo= : 22:42 | comment (0) | trackBack (0)
2009年08月23日
"Stronger Than Pride" by Sade

閑を持て余していた大学生時代の事だったと思う。週末の深夜、というよりももう空は明るみ始めていて、早朝といっていい時分。その部屋に設えてあったTVからは、夜通し、海外アーティストのミュージック・クリップが流れていて、同室のものは皆、観るともなく観ていた。
卓の上には、雀牌が放置されていたのか、山と積まれた吸いさしで灰皿が溢れ還っていたのか、空っぽになっていたボトルが転げていたのか、それは知らない。
ただ、画面の向こうでは、白い大柄のトレンチ・コート (Trench Coat) を着込んだ、褐色の女性が、街を闊歩していたのだ。
それが、初めて観たシャーデー・アデュ (Sade Adu) だった。
read details "Stronger Than Pride" by Sade
posted =oyo= : 15:05 | comment (0) | trackBack (0)
2009年07月19日
"NEW YORK" by LOU REED
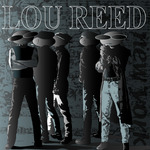
随分と待たされたアルバム。以前、どこかで書いた様な気がするけれども、クルト・ワイル (Kurt Weill) のトリビュート・アルバム『星空に迷い込んだ男/クルト・ワイルの世界 (Lost in the Stars: The Music of Kurt Weill)』 [プロデュース:ハル・ウィルナー (Hal Willner)]で聴く事が出来た『セプテンバー・ソング (September Song)』が最高だったのだ。
素材である原曲によりかかりもせず、かといって、己の音楽性を殊更に際立たせない、そのアプローチがかっこ良かった。
原曲の持つ、甘美なメロディーは一切姿を現さない筈なのに、その曲が描く叙情は総て兼ね備えている。
ロックンロール (Rock & Roll)。
一言で言えば、それ以外のナニモノでもないその曲は、クルト・ワイル (Kurt Weill) のロックンロール (Rock & Roll)でもあると同時に、ルー・リード (Lou Reed) のロックンロール (Rock & Roll)そのものでもあったのだ。
read details "NEW YORK" by LOU REED
posted =oyo= : 16:22 | comment (0) | trackBack (0)