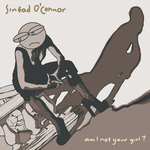2014年04月20日
“SOLID STATE SURVIVOR” by YELLOW MAGIC ORCHESTRA
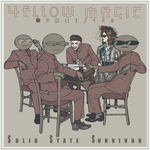
アルバム・ジャケットから窺い知る事は、ここにあるのは似非や騙りや剽窃や偽物や擬きやエピゴーネン (Epigonen) やシュミラクラ (Simulacra) であって、真実や真相は一切、その正体を顕していないのだ。
read details “SOLID STATE SURVIVOR” by YELLOW MAGIC ORCHESTRA
posted =oyo= : 09:24 | comment (0) | trackBack (0)
2014年03月16日
『カレッジ・ツアー (College Tour)』 by パティー・ウォータース (PATTY WATERS)

例えば仮に、『無人島レコード (Desert Island Discs)』を10枚選べと、ぼくが謂われたとしたら残念ながら、この作品は決して選ばれない。だけれども、選ぶべき盤の枚数を100枚に拡大してもらえるとしたら、その選択の過程で2, 3枚は選ばれてしまうのに違いない。
つまり、一度、選択肢のうちのひとつとして挙げた事を忘れ去ってしまって、何度もその候補に挙げてしまう、と謂う訳だ。
変な喩え話だけれども。
read details 『カレッジ・ツアー (College Tour)』 by パティー・ウォータース (PATTY WATERS)
posted =oyo= : 10:21 | comment (0) | trackBack (0)
2014年02月16日
“Smile!! It’s not the end of the world” by VIBRASTONE
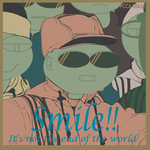
ビブラストーン (Vibrastone) とは、近田春夫 (Chikada Haruo) ともう一人のラッパー、ドクター・トミー (Dr. Tommy) を中心として、音楽的な側面に関してはオト (Oto) が全面にイニシアティヴを握った、総勢12人による人力ラップ・グループ。
大雑把に説明しようとすれば、こんな言辞となるだろう。
個人的にはリアル・タイムな体験もあるせいだろう、近田春夫 (Chikada Haruo) のこれまでの活動の中で、最もダイナミズムに溢れたモノと思っている。
1987年から1996年の間、活動し、全4作品のアルバムを発表している。
今回取り上げるのは、その第2作。1993年に発表された。
read details “Smile!! It’s not the end of the world” by VIBRASTONE
posted =oyo= : 08:15 | comment (0) | trackBack (0)
2014年01月19日
『Music For Silent Movies』 by 上野耕路 (Koji Ueno)
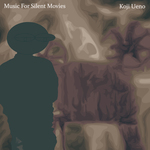
無声映画 (Silent Film) の、そこには存在しない筈のサウンドトラックを制作する試み、その作品集である。
read details 『Music For Silent Movies』 by 上野耕路 (Koji Ueno)
posted =oyo= : 09:36 | comment (0) | trackBack (0)
2013年12月15日
"T-REX GREAT HITS 1972 - 1977 : THE A-SIDES AND THE B-SIDES" by T-REX
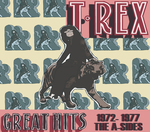
冒頭5曲でやられてしまう。そして、これで充分ではないか、と想ってしまう。
read details "T-REX GREAT HITS 1972 - 1977 : THE A-SIDES AND THE B-SIDES" by T-REX
posted =oyo= : 08:26 | comment (0) | trackBack (0)
2013年11月17日
『彩 [エイジャ] (AJA)』 by スティーリー・ダン (Steely Dan)
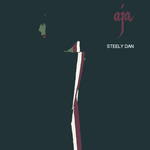
これまでに、何度も何度も聴いた事だろう。そして、恐らく、何度も何度も聴く事になるだろう、これからもずっと。
read details 『彩 [エイジャ] (AJA)』 by スティーリー・ダン (Steely Dan)
posted =oyo= : 11:10 | comment (0) | trackBack (0)
2013年10月20日
"THE RUTLES" by THE RUTLES
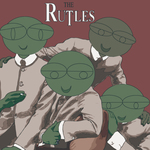
ザ・ビートルズ (The Beatles) が糞虫 (Dung Beetle) でない様に、ザ・モンキーズ (The Monkees) が猿公 (Monkey) でない様に、ザ・ラトルズ (The Rutles) はロックンロール (Rock And Roll) の古典『シェイク・ラトル・アンド・ロール (Shake, Rattle And Roll)』 [オリジネイターはビッグ・ジョー・ターナー (Big Joe Turner) 1954年発表] でもお馴染の「ガラガラ (Rattle)」という単語を捻って命名された。
では、モンティ・パイソン (Monty Python) と謂う名称は、どこから来たのだろう。
read details "THE RUTLES" by THE RUTLES
posted =oyo= : 12:37 | comment (0) | trackBack (0)
2013年09月15日
"mothership connection" by PARLIAMENT

1アーティスト1作品というのが慣行的になっているこの連載だけれども、それを踏まえて考えてみると、果たしてこの作品でいいのだろうか、という逡巡は、こうして記事を書き始めている今も、続いているのだ。
read details "mothership connection" by PARLIAMENT
posted =oyo= : 03:01 | comment (0) | trackBack (0)
2013年08月18日
『永遠の詩集 [シンニード・シングス・スタンダード] (am I not your girl?)』 by シンニード・オコナー (Sinead O'connor)
現在の彼女の日本語表記は、シネイド・オコナー (Sinead O'connor) に統一されつつあるのだけれども、1987年にデヴューした当初のそれは、シンニード・オコナー (Sinead O'connor) であり、AmazonやiTunes Storeでの表記は、シニード・オコナー (Sinead O'connor) である。
ぼくがこの作品を購入した際の表記は、上掲の様にシンニード・オコナー (Sinead O'connor) だったので拙稿のタイトルは、それに従ったものである。
以降、アーティストとしての彼女を指し示す場合は、シネイド・オコナー (Sinead O'connor) と表記する事にする。
read details 『永遠の詩集 [シンニード・シングス・スタンダード] (am I not your girl?)』 by シンニード・オコナー (Sinead O'connor)
posted =oyo= : 06:25 | comment (0) | trackBack (0)
2013年07月21日
"THE GREATEST LIVING ENGLISHMAN" by MARTIN NEWELL
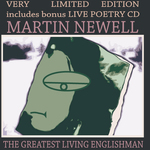
この作品に出逢った時の、目眩めいたモノの感触は今でも憶えている。
外資系の大手輸入盤店の、どこに行っても、新着コーナーの最前列にこのCDが並んでいたのである。俗に言う"面出し"というやつである。
そして、整然と並べられているCDの脇に添えられた、手書きポップには、殆ど総てと言っていい、共通の言葉が書き連ねてあったのである。
アンディ・パートリッジ (Andy Partridge)・プロデュース、と。
1993年の事である。
read details "THE GREATEST LIVING ENGLISHMAN" by MARTIN NEWELL
posted =oyo= : 09:46 | comment (0) | trackBack (0)
2013年06月16日
『オリジナル・ジェリー・マリガン・カルテット (GERRY MULLIGAN QUARTET)』 by ジェリー・マリガン (GERRY MULLIGAN)

彼らの存在を初めて知ったのは、ここでも映画『真夏の夜のジャズ (Jazz On A Summer's Day) 』 [バート・スターン (Bert Stern)・アラム・A・アヴァキアン (Aram Avakian) 監督作品 1960年制作] である。
勿論、その映画では、リーダーであるジェリー・マリガン (Gerry Mulligan) [bs] と共にフロントを勤めるのは、本作品の一方の主役、チェット・ベイカー (Chet Baker) [tp] ではない。アート・ファーマー (Art Farmer) [tp] だ。
そして、この作品でドラムス (Drums) を担当しているチコ・ハミルトン (Chico Hamilton) [dr] は、その映画では、自身のユニット、チコ・ハミルトン・クインテット (Chico Hamilton Quintet) として、最も印象深い演奏を聴かせてくれる [彼の作品はここで既に紹介済みだ]。
なにせ、本作品が収録されたのは1952年。映画が撮影された1958年から6年も前の作品だ。
参加メンバーそれぞれに様々なドラマがあったとしても不思議ではない。
read details 『オリジナル・ジェリー・マリガン・カルテット (GERRY MULLIGAN QUARTET)』 by ジェリー・マリガン (GERRY MULLIGAN)
posted =oyo= : 21:46 | comment (0) | trackBack (0)
2013年05月19日
"STAIN" by LIVING COLOUR
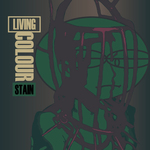
ファンカデリック (Funkadelic) の幾つもある名曲のひとつに『ファンク・バンドがロックを出来ないなんて誰が言ったんだ (Who Says A Funk Band Can't Play Rock?!)』 [アルバム『ワン・ネイション・アンダー・ア・グルーヴ (One Nation Under A Groove)』収録 1978年発表] がある。
リヴィング・カラー (Living Colour) というバンドは、この曲の主張を忠実に実行しようという試みである。
read details "STAIN" by LIVING COLOUR
posted =oyo= : 16:49 | comment (0) | trackBack (0)
2013年04月21日
『No.17 (No17)』 by 小泉今日子 (kyoko Koizumi)
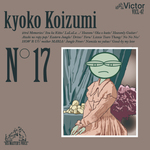
何故、小泉今日子 (Kyoko Koizumi) だけが特別だったのか、そこから書き始めなければならないのだろうか。
read details 『No.17 (No17)』 by 小泉今日子 (kyoko Koizumi)
posted =oyo= : 13:21 | comment (0) | trackBack (0)
2013年03月17日
"SURREALISTIC PILLOW" by JEFFERSON AIRPLANE
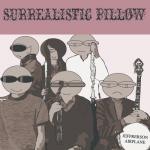
例えば『サムバディ・トゥ・ラヴ / Somebody To Love』と聴いて、どのアーティストのどの曲を想い浮かべるのか、という問題は、実はとっても重要なモノではないだろうか。
read details "SURREALISTIC PILLOW" by JEFFERSON AIRPLANE
posted =oyo= : 11:10 | comment (0) | trackBack (0)
2013年02月17日
"DEATH CERTIFICATE" by ICE CUBE
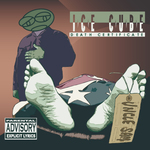
1970年代後半が、英国にとっての駄目な時季でそれに呼応する様にパンク (Punk) 〜ニュー・ウェイヴ (New Wave) という動きが勃興した、それと同様な事が10年後、米国に興ったのではないだろうか。
と、1991年発表の此の作品のジャケットを、久しぶりに観て、そう想った。
read details "DEATH CERTIFICATE" by ICE CUBE
posted =oyo= : 09:52 | comment (0) | trackBack (0)
2013年01月20日
『ウィ・スリー (WE THREE WITH PHINEAS NEWBORN, PAUL CHAMBERS)』 by ロイ・ヘインズ (ROY HAYNES)

一見、三者均等のユニット名の様に思えてしまうかもしれないが、アルバムのクレジットをよく読めば解る様に、本作品のリーダーは、ロイ・ヘインズ (Roy Haynes)。ドラマーが主役となるべき作品である。
read details 『ウィ・スリー (WE THREE WITH PHINEAS NEWBORN, PAUL CHAMBERS)』 by ロイ・ヘインズ (ROY HAYNES)
posted =oyo= : 08:48 | comment (0) | trackBack (0)
2012年12月16日
"Poupee de son" by France Gall

このベスト盤が発売された当時は、本作品と同時にCD5枚組のよりコンプリートに近いものも、発売された [ヴィジュアル・デザインは両者共通のモノである]。
read details"Poupee de son" by France Gall
posted =oyo= : 07:17 | comment (0) | trackBack (0)
2012年11月18日
『ギター・ソロ (GUITAR SOLOS)』 by フレッド・フリス (FRED FRITH)

このアーティストの存在を最初に知ったのが、本体であるヘンリー・カウ (Henry Cow) からなのか、それともそれをそれぞれの方向へと先鋭化させた先のユニット、アート・ベアーズ (Art Bears) からなのかマサカー (Massacre) からなのか、八木康夫 (Yasuo Yagi) からなのか、"ユーロ・ロック・マガジン (Euro Rock Magazine)"時代の雑誌『フールズ・メイト(Fool's Mate)』からなのか、雑誌『ロッキング・オン (Rockin' On)』での竹場元彦の記事からなのか、記憶はとっても曖昧なのだ。
もしかしたら、彼の初来日コンサートという情報からかも知れない。
read details 『ギター・ソロ (GUITAR SOLOS)』 by フレッド・フリス (FRED FRITH)
posted =oyo= : 10:53 | comment (0) | trackBack (0)
2012年10月21日
Bill Evans Trio Sunday at the Village Vanguard Featuring Scott La Faro
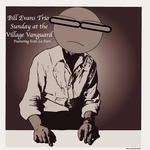
初めて買ったビル・エヴァンス (Bill Evans) の作品は『ポートレイト・イン・ジャズ (Portrait In Jazz)』 [1959年発表] で、それからすこしづつ、『ワルツ・フォー・デビイ (Waltz For Debby)
』 [1961年発表]、本作品である『サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード (Sunday At The Village Vanguard)
』 [1961年発表]、そして『エクスプロレイションズ (Explorations)
』 [1961年発表] と、増えて行ったのだけれども、そこから先は、一向に増える気遣いはない。
read details Bill Evans Trio Sunday at the Village Vanguard Featuring Scott La Faro
posted =oyo= : 10:47 | comment (0) | trackBack (0)
2012年09月16日
『マイルス・アット・フィルモア (MILES DAVIS AT FILLMORE)』 by マイルス・デイビス (MILES DAVIS)

「本作を聴くと、あの時代が眼前に出現する。あの時代の空気までがモワ〜ッと漂ってくる」
「ここで、早くも殺気が漂う。マリファナの煙がたちこめる、モワ〜ッとした空気が伝わる」
「そのクライマックスに、マイルスが鋭い一音を吹き放ちながら出現、《フィルモア》の暑く長い夏<以下略>」
上に引用した文章は、総て中山康樹著『マイルスを聴け!』での本作品に関する記述であって、この作品を語るのには、上に引用した部分だけで充分ぢゃあないだろうか、という、そんな気がするのである。
read details 『マイルス・アット・フィルモア (MILES DAVIS AT FILLMORE)』 by マイルス・デイビス (MILES DAVIS)
posted =oyo= : 13:57 | comment (0) | trackBack (0)